この記事の目次
ゼロエミッションとは?
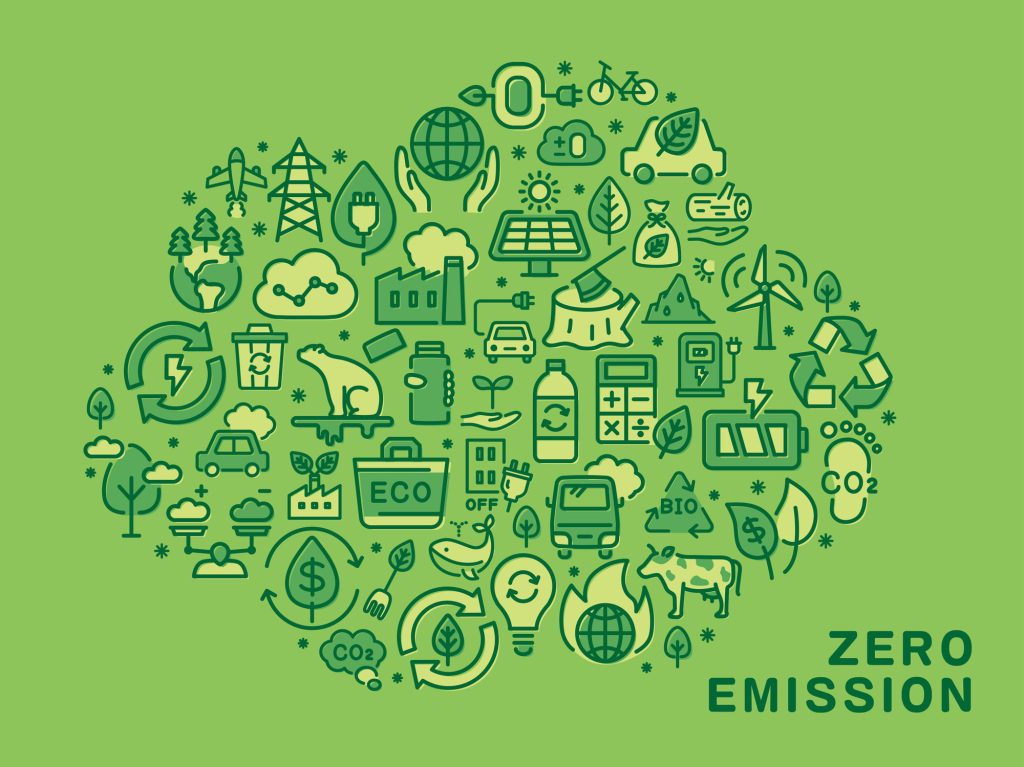
ゼロエミッションとは、1994年に国際連合大学によって発足した「人間の産業・経済活動から発生する廃棄物の排出(エミッション)を可能な限りゼロに近づける」という考え方のことです。
現在の廃棄物を出し続ける産業のあり方は、地球の資源を使い切ってしまう、最終処分場における埋め立て量の限界を超えてしまうなどのリスクがあり、持続不可能と言われています。
ゼロエミッションは廃棄物を減らすだけでなく、産業活動から出る廃棄物を別の産業が資源として再利用するなど、社会全体で資源を循環させる持続可能な経済システムを構築することを目指しているのです。
近年では、CO2(二酸化炭素)などの温室効果ガスを含む、あらゆる排出物をゼロにするという広い意味で使われています。
カーボンニュートラルとの違い
ゼロエミッションとカーボンニュートラルは、対象とする排出物の範囲が異なります。ゼロエミッションはあらゆる廃棄物を限りなくゼロにするという考え方であるのに対して、カーボンニュートラルはその一部である温室効果ガスに特化した考え方です。
温室効果ガスとは、大気の熱を吸収する性質を持つガスのことで、代表的なものにCO2やメタンなどがあります。異常気象を引き起こす地球温暖化は、大気中の温室効果ガス濃度が高まり、地表の温度が過度に上昇していることが原因と考えられています。
そのため、カーボンニュートラルは、人間の活動によって発生する温室効果ガスの排出量から、植林・森林管理やCCS(二酸化炭素回収・貯留)技術などによる吸収量を差し引いて、実質的に排出量をゼロにする(ニュートラルにする)ことを目指しています。
脱炭素との違い
「脱炭素」とは、温室効果ガスのなかでも、特に影響が大きいCO2(二酸化炭素)の排出量を社会全体で実質ゼロにすることを目指す取り組みです。
太陽光や風力・水力・火力といった再生可能エネルギーへの転換をはじめ、効率の良い機器やシステムの導入による省エネルギー化、電気自動車の普及や次世代エネルギーの活用による非化石燃料へのシフトなどが、主な取り組みとして挙げられます。
このように、CO2の排出量削減に特化した脱炭素は、ゼロエミッションを達成するための重要な要素の一つといえるでしょう。
今、ゼロエミッションが注目を集める理由
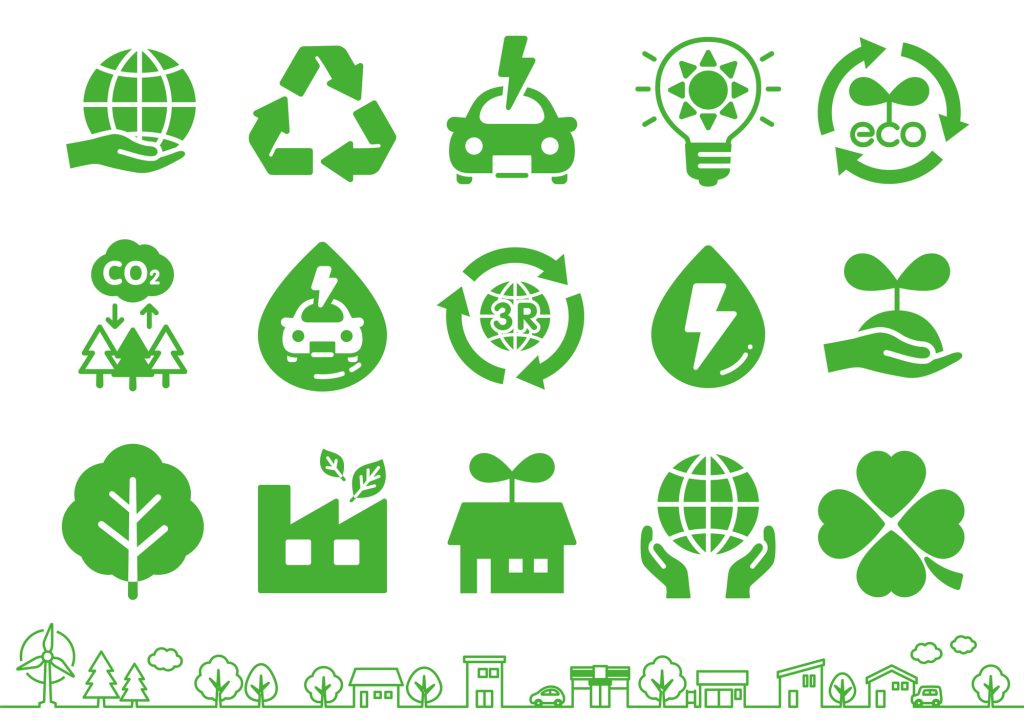
ゼロエミッションが注目を集める背景には、深刻化する気候変動と資源の枯渇という、大きな課題があります。
2015年に、パリ協定やSDGs(持続可能な開発目標)などの国際的な枠組みができたことで、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを削減する動きが加速しました。ゼロエミッションは、その温室効果ガス削減目標を実現するために不可欠な考え方として注目されています。
また、ゼロエミッションのもう一つの重要な側面は、廃棄物を資源として再利用する「循環型社会」の構築です。廃棄物の最終処分場がひっ迫し、資源が限られているなかで、ゴミを減らすだけでなく、再利用やリサイクルを徹底する仕組みづくりが求められています。
ゼロエミッションは、こうした循環型社会を実現するための重要なアプローチとされているのです。
日本と世界のゼロエミッションへのロードマップと目標

ゼロエミッション実現のためには、国境を越えた協力と長期的な取り組みが欠かせません。ここでは、世界各国や日本で行われている具体的な取り組みについて、紹介していきます。
世界のロードマップと目標
ゼロエミッションの実現は、2015年に採択されたパリ協定によって、一部の先進国だけでなく、中国やインドなどの新興国も含めた国際社会全体の共通目標となりました。
パリ協定では、世界の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて「2℃より十分低く保つ」と共に、「1.5℃に抑える努力をする」という世界共通の長期目標が掲げられました。加えて、各国が自国の状況に応じて、温室効果ガスの削減目標を自主的に設定することになっています。
EU(欧州連合)では、包括的な政策パッケージ「欧州グリーンディール」を掲げ、2050年までに「気候中立(温室効果ガス排出実質ゼロ)」を達成することを法制化。
また、世界最大の温室効果ガスの排出国である中国は、「2060年までにカーボンニュートラルを達成する」と宣言。この目標を達成するため、中国では太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの導入を急速に進めています。
日本のロードマップと目標
日本政府は、「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする(カーボンニュートラル)」ことを宣言しました。
この目標達成のため、太陽光・風力・地熱などの再生可能エネルギーの主力電源化、住宅や建築物の断熱性能の向上などによる省エネルギー化の徹底を推進。
また、水素やアンモニアなどの次世代エネルギー技術の活用への取り組みなどを進めています。
ゼロエミッション達成に向けた主要な取り組み

ゼロエミッション達成に向けて、日本では国と自治体が連携してさまざまな取り組みを進めています。また、ゼロエミッション実現には、企業による取り組みも不可欠です。ここでは、国や自治体、企業の取り組み事例を紹介します。
国や自治体による取り組み
エコタウン事業
地方自治体が、ゼロエミッションを基本構想とする「エコタウンプラン」を策定し、国の承認を得ることで支援を受けられる制度です。廃棄物削減と資源の循環利用を通じて、産業振興や地域活性化を目的としており、北九州市や富山市など、26の地域が持続可能なまちづくりを推進しています。
※参考:環境省「エコタウンの歩みと発展」
ゼロエミッション東京
東京都が宣言した、2050年までにCO2排出量を実質ゼロにすることを目指す戦略です。エネルギー、都市インフラ、資源、産業などの6分野と14の政策で、具体的な行動計画を進めています。再生可能エネルギーの基幹エネルギー化や水素エネルギーの普及を柱に、2025年には新築建物への太陽光発電設備設置が義務化されました。
※参考:東京都 環境局「ゼロエミッション東京」
企業による取り組み
サントリーホールディングス
サントリーでは、工場で使用する燃料を重油から都市ガスや液化天然ガスに転換し、省エネルギー化を実現。また、太陽光発電設備やバイオマス燃料ボイラーを導入し、国内初のCO2排出の実質ゼロ工場を実現しました。
※参考:サントリーホールディングス「地球とともに歩む未来へ」
大和ハウス工業
大和ハウス工業では、「環境長期ビジョン『Challenge ZERO 2055』」を掲げ、グループ全体で環境負荷ゼロを目指しています。その中で、「まちづくりにおけるCO2の“チャレンジ・ゼロ”」「 事業活動におけるCO2の“チャレンジ・ゼロ”」「サプライチェーンにおけるCO2の“チャレンジ・ゼロ”」などの7つの目標を設定しています。
※参考:大和ハウス工業「環境長期ビジョン」
アスクル
サプライチェーン全体でのCO2排出量削減とネットゼロエミッションを目指し、「2030年CO2ゼロチャレンジ」を掲げています。2017年には、日本企業として初めて「RE100」と「EV100」に同時加盟。2030年までに、RE100ではグループ全体の再生可能エネルギー利用率100%を、EV100ではグループの配送車両を100%電気自動車に転換することを目標としています。
※参考:アスクル「気候変動・脱炭素」
ゼロエミッションの課題と今後の展望

ゼロエミッションの実現には、多くの課題があります。技術面では、廃棄物の再利用に新たなエネルギーが必要となることや、リサイクルの質を向上させるコストがハードルとなっています。
経済面では、脱炭素化に向けて大規模な設備投資や運営コストが必要となるため、中小企業の参入を妨げています。社会全体での理解と合意形成、企業へのノウハウの共有・浸透も重要な課題です。
しかし、国や自治体の支援策と取り組みが企業の行動を後押しし、省エネルギーによるリサイクル技術や再生可能エネルギーの導入が加速すれば、持続可能な社会が実現していくでしょう。
また、脱炭素技術やサービスといった新たなビジネスチャンスが生まれ、経済成長にもつながると期待されています。官民一体となった変革が、ゼロエミッション社会の実現を可能にするのです。
ゼロエミッションのために個人ができることは?

ゼロエミッションと聞くと、国や企業の大規模な取り組みを想像するかもしれませんが、私たち一人ひとりの行動もその実現に貢献できます。
特に、「3R(リデュース・リユース・リサイクル)の徹底」「エネルギーの使い方を見直す」「環境を意識した消費行動を心がける」という3つのポイントを意識して行動することが大切です。
具体的には、下記のような行動が挙げられます。
- 節電・節水を心がける
- 自治体のルールに従って、ゴミを正確に分別する
- 公共交通機関の利用やエコカーの選択をする
- 食品ロスを削減する
- マイバッグやマイボトルを利用する
- エコマークのついた商品や環境に配慮した製品を選択する
- 再生可能エネルギー由来の電力を供給する電力会社を選ぶ
- ゼロエミッションを推進する企業や活動を支援する
▼関連記事はこちら
3Rとは?リデュース・リユース・リサイクルの意味と今日からできること
サステナブルなくらしを始めよう!気軽にできる8つの方法とアイテムを紹介
フードロス(食品ロス)の現状と課題、私たちができることは?
毎日の行動でゼロエミッションの達成に貢献しよう!
ゼロエミッションは、地球温暖化による気候変動を緩和することはもちろん、持続可能な社会を構築するためにも重要な取り組みです。
ゼロエミッションの実現には、国や企業だけでなく、私たち1人ひとりの意識や行動が大切です。未来のために、今日からゼロエミッションを後押しする行動を始めてみませんか? 小さな行動の積み重ねが、いずれ大きな変化を生み出します。

